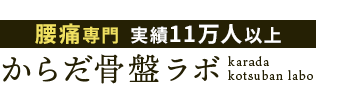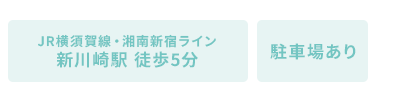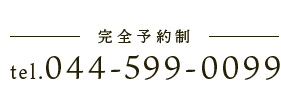【関節構成運動とは?】筋膜リリースより大事な「関節の秘密」
【関節構成運動とは?】筋膜リリースより大事な「関節の秘密」

関節構成運動
「筋膜が硬いからストレッチをしましょう」「筋肉を鍛えれば痛みは改善します」——これは確かに一理あります。
ですが、関節の本質的な動きを知らずにケアしても、痛みや不調が長引くことがあるのをご存知でしょうか?
それを左右しているのが、「関節構成運動(joint play)」と呼ばれる動きです。
今回は、整体師の立場から“関節の滑らかな動き”の真実と、見逃されがちなリスク、そしてその解決法をわかりやすくお伝えします。
■ 驚きの事実:「関節はただ曲がるだけ」ではなかった!
人間の関節は、たとえば膝を曲げる・伸ばすという単純な動きの裏側で、
「滑り」「転がり」「回旋」といった複雑な動きが同時に起こっています。
この中でも、関節面同士の「滑り」や「転がり」を正しく誘導する運動こそが関節構成運動。
たとえば、膝関節が曲がる際、脛骨(すねの骨)は大腿骨(ももの骨)に対して約5〜10mmほど滑りながら動くことが確認されています(※日本整形外科学会資料より)。
このわずかな滑走運動がスムーズに行われないと、可動域が制限され、無理に動かそうとした結果、炎症や軟骨の摩耗を招くこともあります。
■ リスク:構成運動の不足は「痛みの根本原因」になる
関節構成運動が不足すると、見た目では関節が動いているように見えても、
中では関節面が擦れ合い、関節包や軟骨に負担がかかっています。
これは実際の臨床でもよくあるケースで、「筋トレもストレッチもしているのに痛みが変わらない」「可動域は広がったのに違和感がある」という方の多くは、この関節構成運動が適切に働いていないのです。
さらに驚くべきデータがあります。
国立長寿医療研究センターの調査では、60歳以上の方の約60%に関節構成運動の低下が認められたという報告も。これは年齢とともに関節包や靱帯の柔軟性が落ち、滑りや転がりが制限されることに起因します。
その結果、関節内圧が高まり、腰・膝・股関節・肩などの痛みや炎症が慢性化しやすくなります。
■ 整体で“滑らかな動き”を取り戻すことは可能です
関節構成運動の評価と調整には専門技術が必要です。
当院では、徒手療法(マニュアルセラピー)により、関節面のごくわずかな滑走運動を安全に誘導します。
たとえば、膝の屈伸が困難な方に対し、膝蓋骨や脛骨の滑りを細かく調整することで、一回の施術で可動域が10〜20度改善した例も多数あります。
筋肉をいくら緩めても改善しない違和感や、ストレッチをすると逆に痛みが出る方には、
この「構成運動」へのアプローチがカギとなることが非常に多いのです。
■ 結論:筋トレやストレッチの前に「関節そのものの動き」を見直そう
痛みや可動域の低下に悩むすべての方へ。
筋肉や骨格ばかりに注目していませんか?
本当の問題は、“関節がどのように動いているか”。
関節構成運動の乱れがあると、筋トレやストレッチの効果も半減します。
まずは専門家による評価を受け、「関節が滑らかに動いているか」をチェックすることが、痛みの根本改善への第一歩です。
▼このようなお悩みがある方はご相談ください▼
-
腰や膝の痛みがなかなか取れない
-
ストレッチやマッサージで一時的によくなるが再発する
-
可動域は広がったのに違和感や痛みが残る
-
整形外科では「異常なし」と言われたけどつらい
関節の“本来の動き”を取り戻せば、体はもっと楽になります。